
ぼくの好きなゲームのひとつに「聖剣伝説 レジェンドオブマナ」という作品がある。いわゆるアクションロールプレイングゲームなのだが、仕組みが少し変わっている。
1つの世界のなかで主人公を操作するのだが、物語は1つではなく、膨大な短編ストーリーが積み重なってできあがっている。ぼくらの現実世界のようなものだ。日々、物語は溢れている。
その中あるひとつの物語。「レイチェル」という。
プレイしたのはずいぶん昔で、あの頃のぼくはまだ子どもだった。少しは歳をとったぼくが、最近になってこの物語に触れて、涙を流すことになろうとは、想像もしていなかっただろう。
マーク一家の物語「レイチェル」
物語は道具屋の一家である「マーク家」を中心に巻き起こる。
詳しくは、できれば映像を見てもらったほうが共感できるので、ぜひ以下の動画を見てもらえたら嬉しい。ゲーム実況付きではあるが、とても丁寧に物語の背景を説明してくれるので、理解の助けになるだろう。
マーク一家は「父:マーク」「母:ジェニファー」「娘:レイチェル」「魔法生物(店番):ティーポ」の4人。
父親のマークは、外見とは反対に、とても気が小さい性格。良き夫、良き父親でありたいと思っていて、娘のレイチェルのことを溺愛している。昔は宇宙に行くのを夢見ていたが、娘が大きくなるにつれて夢を語ることは減っていったそうだ。
娘のレイチェルは、昔はおてんばであったが、今では言葉も少なくなり、すっかり殻にこもるようになってしまった。家族は嫌いではないが、居心地を悪く感じており、家にいたくない。
そんなあるとき、レイチェルは書き置きひとつを残して、魔法都市に出ていってしまう。主人公が魔法都市に向かうが、そこにレイチェルの姿はなく、実験に勤しむ生徒がいるだけであった。
そうこうしているうちに、マーク家にレイチェルは帰ってきた。しかしどうやら様子がおかしい。そこには、今までないほど多弁で明るく、父親と仲良くするレイチェルがいた。
様子が変なことに感づいているが、確信が持てないマーク。しかし、そこでマークは意を決してレイチェルに問いかける。
「なぁレイチェル。キミは本当にレイチェルかい?」

するとレイチェルは答える。「私の名前をつけたのはあなた。あなたが私をレイチェルと呼ぶ限り、私はレイチェルだわ」

それを聞いて、マークは再び、自分の抱いている疑念を投げかける。「キミは本当は、私たちの娘のレイチェルじゃないような気がするんだ……」

そこでレイチェルが種を明かす。「魔法学校で、私とレイチェルは身体を交換したの。あなたの言う『ホントのレイチェル』は魔法学校にいるってことになるかしらね」

「じゃあ、やっぱりキミは本当のレイチェルじゃないんだね!?」少し嬉しそうにマークが言う。

すると、レイチェルの姿をしたその女の子は、こう言い放った。
「あ〜あ、バカバカしい。自分の娘って誰のことを言ってるの?」
「あなたがイメージしているような、あなたの娘は、この世界のどこにもいないわ」
「あなたは自分の娘が誰であるかさえ、わかってないのね」

マーク一家を取り巻くこの物語は、言葉で語るよりもっと深く、優しさと慈愛に満ちていて、それでいてほんのり悲しいお話。事の顛末は、ぜひ動画で続きを見てもらいたい。
ぼくのイメージしている、ぼくの娘
ぼくは娘にどうなってもらいたいのだろう。そんなことを、幼稚園に入れる前に、よく妻と話をしていた。
「優しい子がいいな」「思いやりのある子に」「一生懸命で」「悪いことを悪いと言えるような」「誰に流されるのではなく、自分が進みたい道に」
「彼女が一番、幸せである形を」
心から願っていた。いまもそうだ。彼女がしたいことを好きなようにさせてあげられるように、ぼくら親は、いつでも「選択肢」をあげようと。彼女が選べるように。そして、選んだ道を進めるように。
しかし、ぼくは少し彼女に近づきすぎていたのかもしれない。好きという気持ちが強すぎて、最近は「こうあってほしい」と、勝手なぼくの理想の娘を、彼女に押しつけていたのかも。
いや、いまはまだ、押し付けてはいない。そこまでではない。
でも、彼女が大きくなっていって、ぼくがもっともっと近づいていったのなら、ぼくは彼女を彼女として見てあげられなくなっていたかもしれない。
理想の娘という幻想を押し付けて、彼女を彼女以外のナニカにしてしまうところだったのかも——。
この気持ちを、いま持てたことが、ぼくは本当にうれしかった。好きという気持ちが、これほどまでに人を傷つけるのだと、気がつけてよかった。
順番を間違えてはいけないんだよね、きっと。
ぼくは娘が好きだ。
「優しくて」
「思いやりがあって」
「一生懸命で」
「悪いことを悪いと言えて」
「誰に流されるのではなく、自分が進みたい道をすすめる」
そんな形容詞が頭についた娘が好きなんじゃない。
ただただ、ぼくは彼女が好きなのだ。その気持ちだけを、ぼくは忘れずにいなければならない。
執筆後記
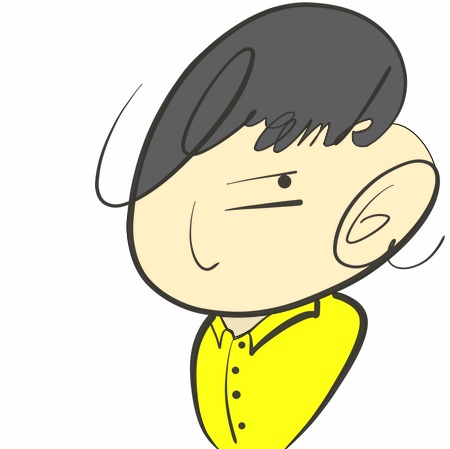
子供の頃はなんとも思わなかったものが、この歳、この立場になって初めて、深くココロに突き刺さるってことが、結構頻繁にあります。ので、昔の思い出の品を見返す機会は、大切だと思うわけです。

